お酒の免許|酒類製造業・販売業の事業譲渡の手続き
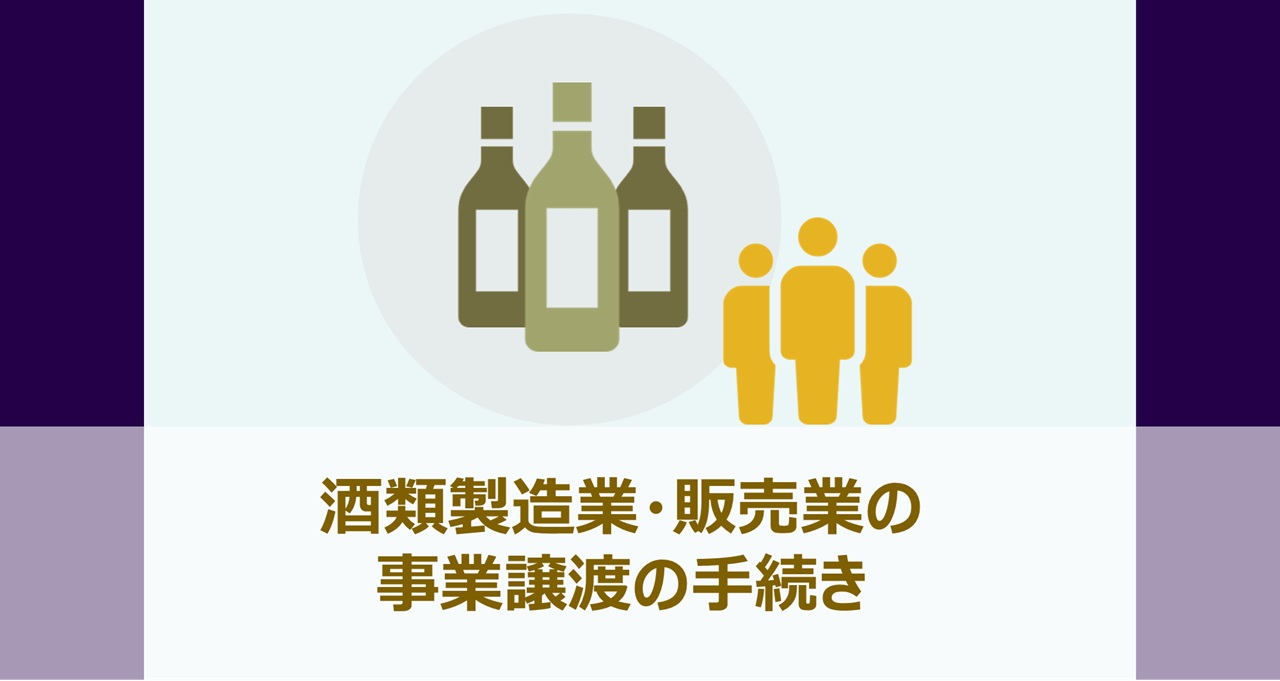
お酒の製造業(又は販売業)を営む個人事業主の方がその事業を譲渡した場合で、譲受人が引き続き同じ場所でその製造業(又は販売業)をしようとする場合は、製造場(又は販売場)の所在地の所轄税務署長に申告する必要があります。
事業の譲受人の要件
次の2つの要件を満たす人が、事業を譲り受けることができます。
- 事業譲渡を行う人の親族、又は、譲渡対象事業で3年以上働いている従業員
- 酒税法10条の欠格要件に該当しないこと
親族の範囲
事業を譲り受けることができる親族とは、民法第725条に定められている次の人のことを意味しています。
- 六親等内の血族
- 配偶者
- 三親等内の姻族
酒税法10条の欠格要件
事業譲渡の場合には、通常の新規申請の場合に比べて要件が緩和されており、譲受人が下表の欠格要件(酒税法第10条第1号から第3号まで及び第6号から第8号)に該当しない場合には、その譲受人は、その事業譲渡のときにおいて、譲渡人が受けていた酒類の製造免許(又は販売業免許)を受けたものとみなされます。
なお、欠格要件に該当するかどうかの判定は、事業譲渡の時において該当していたかどうかによります。
| 酒税法第10条 | 欠格要件 |
|---|---|
| 第1号 | 酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消された日から3年を経過していない場合 |
| 第2号 | 法人の免許取消し等前1年内にその法人の業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年を経過していない場合 |
| 第3号 | 申請者が未成年者でその法定代理人が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合 |
| 第4号 | 申請者等が法人の場合で、その役員が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合 |
| 第5号 | 販売場の支配人が欠格事由(1、2、7~8号)に該当する場合 |
| 第6号 | 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けている場合 |
| 第7号 | 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法若しくはアルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税通則法等の規定により通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していない場合 |
| 第7号の2 | 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等適正化法(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る。)暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない場合 |
| 第8号 | 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない場合 |
| 第10号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合 |
事業譲渡申告で必要な書類
お酒の製造業または販売業の事業譲渡申告で必要となる書類は下表のとおりです。
| 申告書類 | 留意事項 |
|---|---|
| 事業譲渡申告書 | ー |
| 事業譲渡に関する契約書その他の事業譲渡の事実及び年月日を証する書類の写し | 事業譲渡の事実及び年月日が証されていること |
| 免許要件誓約書(酒税法10条の規定に該当しない旨) | 酒税法第10条の第1号から第3号まで及び第6号から第8号までの規定に該当しない旨が誓約されていること |
| その他参考となるべき書類 | (1) 譲渡者の親族の場合は、民法第725条に定める親族(六親等内の血族、配偶者又は三親等内の姻族)であることが分かる資料(戸籍謄本等)が添付されていること (2) 親族以外の場合は、譲渡対象事業に3年以上従事している(過去に従事していた年数を含む。)者であることが分かる資料(源泉徴収票の写し等)が添付されていること |
| 事業譲渡の申告書チェック表 | ・確認欄に○印を付して確認しているか ・省略した書類について斜線を引いているか |
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、お酒の小売・卸売・輸出・輸入などを始めたい方を対象に、酒類販売業免許申請の手続き支援を行っております。初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

