お酒の免許|通信販売酒類小売業免許|通信販売でお酒を販売する免許
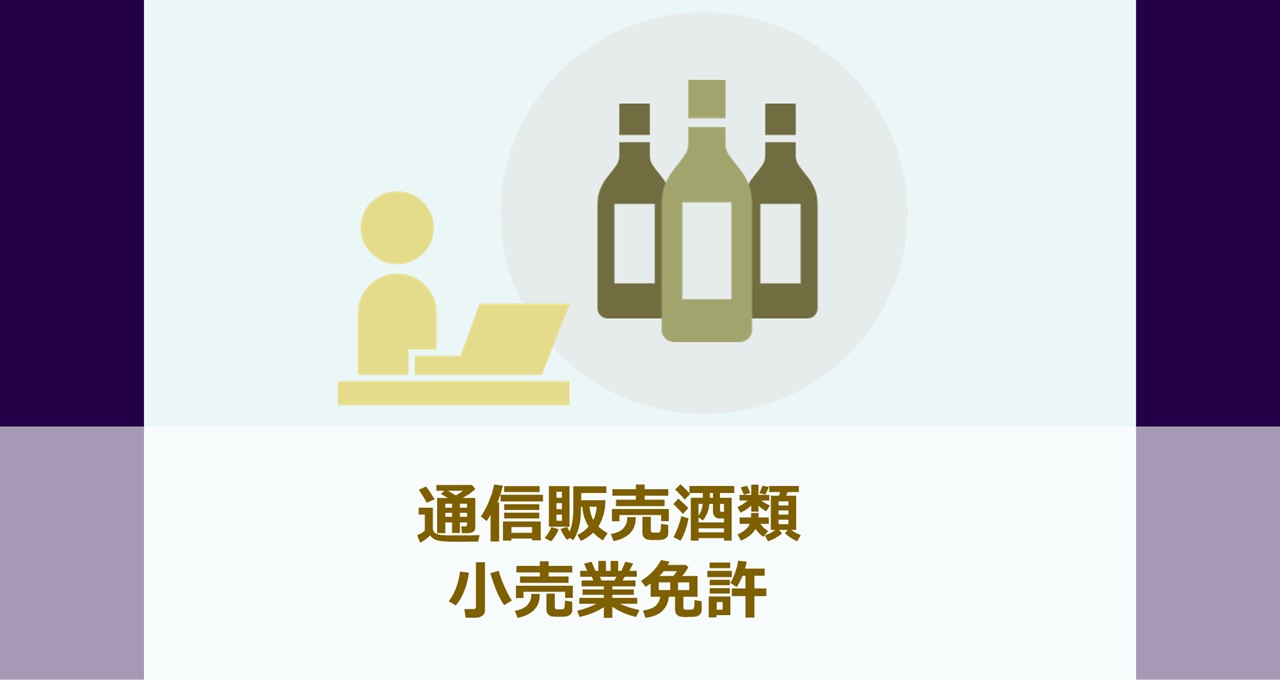
お酒の販売を行うためには、「酒類販売業免許」が必要ですが、その中でもお酒のインターネット販売を行う際に必要となるのが、「通信販売酒類小売業免許」です。
通信販売酒類小売業免許の概要
通信販売酒類小売業免許は、通信販売でお酒を販売(小売)することができる免許です。たとえば、次のような方法でお酒を販売する場合に必要となる免許です。
- インターネット上のECサイトで注文を受け2以上の都道府県の消費者にお酒を販売する
- インターネット上のショッピングモールに出店してお酒を販売する
- カタログやチラシを配布して2以上の都道府県の消費者に販売する
- オークションサイトを使って買い取りしたお酒を継続的に2以上の都道府県の消費者に販売する
なお、通信販売酒類小売業免許では、お酒の店頭小売(店頭においてお酒の売買契約の申込みを受けること又は店頭においてお酒を引き渡すことを行う販売)又は1つの都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできません。
また、販売相手は、日本国内の一般消費者(飲食店含む)が対象となります。海外の消費者等へお酒を販売したい場合は、「輸出酒類卸売業免許」が必要となります。
「通信販売」の定義
通信販売とは、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売」と定義されています。
通信販売酒類小売業免許の要件
通信販売酒類小売業免許を取得するためには、「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」といったすべての基準を満たすことが必要です。
人的要件
申請者に、過去において法律違反や税金滞納の事実があるなど、規範意識に欠けているかを判断するための基準です。法人申請の場合は、役員全員について審査されます。
場所的要件
酒類販売を営む販売場が適切な場所に設けられているかを判断するための基準です。
具体的には、申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないことが必要となります。
経営基礎要件
申請者の資金、経験、知識、経営状態などが十分に備わっているかを判断するための基準です。
たとえば、破産手続開始の決定を受けていない(受けても復権を得ている)、税金を滞納していない、1年以内に銀行取引停止処分を受けていない、貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないなど、通信販売酒類小売業を継続することができる経営基盤があることの証明が必要となります。
需給調整要件
通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒は、次のものに限られています。
- 国産酒類のうち、次に該当する酒類
- カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(=特定製造者)が製造、販売する酒類
- 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品に限る)を原料として、特定製造者以外の製造者(大手メーカー)に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類
- 輸入酒類(酒類の品目や数量の制限なし)
販売するお酒が国産酒類の場合は、仕入先が特定製造者であることの証明書を取得して、申請書類として提出しなければなりません。
通信販売酒類小売業免許の申請書類
通信販売酒類小売業免許の申請では、下表の書類が求められます。
| 提出書類 | 留意事項 |
|---|---|
| 酒類販売業免許申請書 | ー |
| 「販売場の敷地の状況」 | 建物の全体図に、申請販売場の位置が明示されていること |
| 「建物等の配置図」 | 申請販売場と一体として機能する倉庫等が明示されていること |
| 「事業の概要」 | 店舗等の広さ、什器備品等について記載漏れがないこと |
| 「収支の見込み」 | 申請販売場の店舗に照らし合わせた合理的な収支見積もりが組まれていること |
| 「所要資金の額及び調達方法」 | 自己資金による場合は資金繰表、資金捻出の根拠説明書又は残高証明書等、融資による場合は金融機関の証明書又は融資者の原資内容を証明する書類を添付していること |
| 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 | 酒類販売管理者の選任予定者の氏名及び年齢等が記載されていること |
| 酒類販売業免許の免許要件誓約書( 通信販売酒類小売業免許申請用) | ・誓約事項に漏れがないこと ・誓約すべき者に漏れがないこと(申請者、申請法人の監査役を含めた役員全員、申請者の法定代理人及び申請販売場の支配人) |
| 申請者の履歴書 | ・申請者が法人の場合には、法人の監査役など、役員全員が添付されていること |
| 定款の写し | 申請者が法人の場合に必要 |
| 契約書等の写し | 土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書(写)、建物が未建築の場合は請負契約書(写)、農地の場合は農地転用許可関係書類(写)を添付していること |
| 地方税の納税証明書 | ・都道府県及び市区町村が発行する納税証明書(未納税額がない旨及び2 年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明)をそれぞれ添付していること ・法人については、証明事項に「特別法人事業税」を含めていること |
| 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | 最終事業年度以前3事業年度分があること (個人の場合には、収支計算書等) |
| 土地及び建物の登記事項証明書 | ・全部事項証明書を添付していること ・申請販売場の建物が複数の土地にかかる場合には、その全ての地番に係る土地の登記事項証明書を添付していること |
| その他参考となるべき書類 | (1)販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書又は製造委託契約書・同計画書等 (2)酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(インターネット等によるものを含む)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等 |
登録免許税
通信販売酒類小売業免許が付与される場合、登録免許税を納付する必要があります。小売業免許の登録免許税の額は、免許1件につき3万円です。
おわりに
行政書士しょうじ事務所は、お酒の小売・卸売・輸出・輸入などを始めたい方を対象に、酒類販売業免許申請の手続き支援を行っております。初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

